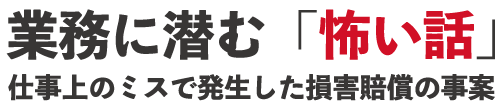運送業はよく「日本の血液」に例えられることがありますが、私たちが日常生活を送るうえでなくてはならない産業です。しかし運送業は長距離運転など業務の性質上事故などのリスクが高い業種なので、過失による損害賠償を心配する人は多いのではないでしょうか。
この記事では運送業で実際にあった、過失による損害賠償問題について取り上げたいと思います。
1.運送業での過失による損害賠償問題

運送業で実際に起きた事故や損害賠償の事例を見ていきましょう。
三菱ふそうトラック・バスタイヤ脱落死亡事件
メディアで代々的に取り上げられたので記憶に新しい人は少なくないと思いますが、2002年に横浜市で大型トラックからタイヤが脱落して親子3人が死傷する事故がありました。その結果三菱ふそうトラック・バスの会長や幹部、部長らが逮捕されました。問われたのは道路運送車両法違反と業務上過失致死傷容疑でした。
問題だったのは三菱の社員が大型車のハブと呼ばれる部分に構造的欠陥があったのを認識しながら必要な対策を怠ったことでした。また国土交通省には虚偽の報告をしていた疑いも持たれています。結果的に最高裁は会社に550万円の支払いを命じました。
高額貨物消失事件
ある運送会社のトラック運転手が高速道路でわき見運転をした結果、追突事故を起こしてしまいました。トラックは横転炎上して積み荷の呉服や毛皮や紳士服などが全焼しました。荷主が高額な貨物であることを伝えていなかったので荷主にも責任が認められましたが、運転手の過失が事故の直接的原因だったので、約1億3千万円の請求が認められました。
協和エンタープライズ事件
ある大型貨物トラックの運転手が高速道路を走っていた際、不注意で衝突事故を起こし死亡しました。しかし死亡した運転手の父親が超過勤務によって事故が誘発されたとして会社を訴えた結果、運転手を雇用していた運送会社の労働時間管理や従業員に対する安全・健康面の配慮義務がかけていたとして過失が認められ、結果的に2,600万円の賠償額が確定しました。
このように運転手側の運転ミスという過失や会社側の安全配慮義務違反という過失が争点となって、損害賠償が発生するケースがいくつも見られます。日本では交通事故が毎日のように発生していますが、運送業に従事する人は管理者側もドライバーも常にリスクを背負っている事を意識しなければなりません。
2.運送業の損害賠償限度額は青天井

日本の運送業には損害賠償に関する厳しい現実があります。国土交通省の「標準貨物自動車運送約款」第47条には以下のような規定があります。
「貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その貨物の引渡すべきであった日の到達地の価額によって、これを定める」
つまり運動業者は預かる貨物の金額すべてに対して責任を負わなければいけないと規定されています。欧米では限度額が定められていて重量当たりの金額が設定されているのに対し、日本では運送業に対する責任の追及が非常に厳しいと言えます。
運送業者が背負わなければいけない責任が大きすぎれば運送業を敬遠する動きが出てしまう恐れがありますし、人手不足になれば運送業者は過重労働を従業員に強いるしかなくなる可能性があります。そうなると先述の事例のような事故を引き起こす恐れも出てきて悪循環になるでしょう。
運送業者は保険に加入するなどの措置を取るのが現実的
運送業に従事している人は上記のような厳しい損害賠償責任に対処するために、運送業向けの保険に加入するのが現実的な対策となります。市販の保険サービスは以下のようなリスクへの賠償を補償してくれます。
- 貨物の損壊
- 預かり貨物の損壊
- 運搬中の破損
- 借用した機材の破損(フォークリフトなど)
- 引き渡し後の事故
運搬作業や積み込み作業などに関する業務上過失を幅広くカバーしてくれるので、万が一の時にも安心感があります。
3 .まとめ
運送業は日本の基幹産業の一つと言えますが、業務上過失やそれに伴う事故や損害賠償のリスクと常に隣り合わせの産業でもあります。従業員であれ管理役人であれ業務上過失によって刑事罰や民事上の損害賠償が請求されるリスクを考えると、絶対に事故を起こさないために安全対策や業務上のリスクヘッジを十分心がける必要があります。
また日本の法律は欧米のそれと比較して運送業者の損害賠償責任に関して厳しい態度を取っているので、共済や保険に加入するなど事前の対策も必要といえます。