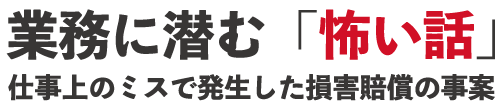「○○ハラスメント」という言葉がにわかに使われるようになっていますが、会社のコンプライアンスに抵触する問題は日常的に起きています。中でも多いと言われているのがパワハラ(パワーハラスメント)です。この記事ではパワハラの意味や実際のトラブル事例、そして損害賠償内容を紹介したいと思います。
1.パワハラの損害賠償の最高額はどれくらい?
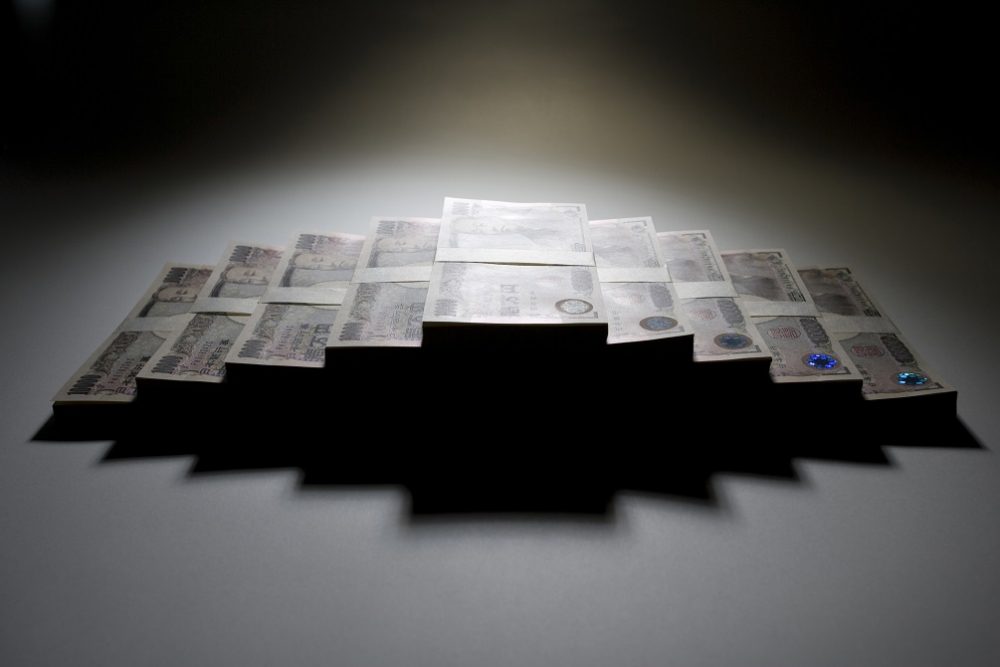
パワーハラスメントとは、同じ職場の労働者に対して業務の適正な範囲を超えて精神的苦痛や身体的苦痛を与えることを意味します。一般的には職務上の地位の優位性や人間関係の優位性を利用して相手に苦痛を与えます。
平成31年6月に公表された「平成30年度:総合労働相談件数統計」によるとパワハラの相談は約82,000件もありました。これらの相談内容すべてがパワハラに当たるのかは不明だとしても、多くの従業員が職場環境に苦痛を感じているのは確かです。
パワハラ被害にあってしまうと通常の業務に大きな支障が出ます。神経質になってしまったり周りから孤立したり、業務に集中できなかったりします。うつ病などを発症することもありますが、少なからず自殺という選択をしてしまう被害者もいます。パワハラはまさに現在の社会における大きな問題です。
パワハラの具体的なトラブル事例と賠償金
では具体的にパワハラのトラブル事例と賠償金を見てみましょう。
・日本ファンド事件
従業員3名が上司からパワハラを受けた結果、そのうちの1人がうつ状態になりました。そのため合同で賠償責任請求をしましたが、上司と会社に対して損害賠償が認められました。1人には60万円の慰謝料と治療費、休業補償、別の従業員には慰謝料40万円、別の従業員には慰謝料10万円の支払いが命じられました。
・公刊物未掲載事件
役員候補の社員が別の社員に対して人権侵害をするパワハラをしていました。被害者はは加害者に対して300万円の慰謝料を請求し、最終的にパワハラとして認められ200万円の支払いが命じられました。
・アジア航測事件
ある女性社員が男性社員に殴られて後遺症が残り2年半の休業を強いられましたが、その途中に解雇されました。賠償責任と解雇無効を訴える訴訟を起こした結果、慰謝料60万円の支払いになりました。
・誠昇会北本共済病院事件
ある看護師が上司から飲み会に誘わて朝まで強引に付き合わされたり、「死ね」や「殺す」といった脅迫めいたメールを送りつけられて自殺しました。遺族は病院と加害者を相手に賠償責任請求をして、両者に500万円の支払いが命じられました。
・青果仲卸会社社員自殺事件
ある女性社員は職場でのいじめやパワーハラスメントを受けて自殺しましたが、訴えが起こされた結果、同社と先輩社員2人に対し約5500万円の支払いが命じられました。女性は自殺前に長期間にわたって繰り返し叱責されていたことが認定されましたが、会社はそれを放置したとして責任が追及されました。
・八鹿病院勤務医自殺事件
長時間労働と上司にあたる医師のパワハラが原因で、ある医師が自殺しましたが、両親は病院側に約1億8千万円の損害賠償を求めました。その結果、運営する病院組合に約1億円の支払いが命じられました。裁判長によると「うつ病の原因となる長時間労働を強いられた上に、上司の医師によるパワハラを継続的に受けていた」と指摘しました。
・イビデン男性社員自殺事件
ある電子部品製造大手の社員が、上司のパワハラや長時間労働が原因と思われる自殺をしました。遺族が同社と上司に対して約1億500万円の損害賠償を求めましたが、同社は請求を全面的に認める「認諾」をしました。
数千万円から億単位の損害賠償もありえる
上記の例のようにパワハラが起きると損害賠償請求を起こされて会社側が多額の賠償金を支払わなければならないケースは少なくありません。会社単位で責任追及されることもあれば、特定の従業員も対象にした損害賠償が請求されることもあります。青果仲卸会社社員の事件や勤務医事件、イビデン事件のように数千万円から1億円にものぼる額になることもあります。
現時点での損賠賠償の最高額がいくらかは断定できませんが、高額損害賠償の事例としては紹介したイビデン事件が有名です。今後ハラスメントに対する社会の認知や規制が進むにつれて、これを上回る額の損害賠償が発生する可能性は十分にあります。
2.まとめ
パワハラは現在、多くの従業員の心身をむしばんでる社会問題です。ハラスメントを題材にしたドラマなども人気になっていますが、今後損害賠償請求が多くの労働者から起こされる可能性は高いです。賠償金だけでなく、裁判になれば会社のイメージも大きく損なわれるでしょう。
ですから、会社はコンプライアンスを徹底して社内の風通しをよくする努力をしなければなりません。社員の福祉に配慮することが会社の発展につながるということをよく考えて、社員が悩みを打ち明けられる機会を作ったり、十分な福利厚生を受けられるようにする必要があります。定期的な社員教育を通して会社全体のモラルを高めていきましょう。