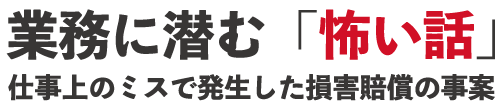「ものづくり大国日本」とよく言われますが、日本は製造業の分野において世界から絶大な信頼を得ている国です。従事者もかなり多く、「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」によると2018年の就業者6,694万人の中で製造業に就いている人は全体の15.9%にあたる約1,060万人もいました。
製造業はまさに日本の基幹産業となっていますが、製造業に関してたびたび大きな問題になるのは製品の不具合や機械操作のミスなどです。そこでこの記事では製造業における損害賠償の事例を紹介したいと思います。
1.製造業の損害賠償の事例

製造業に関する訴訟や判例はたくさんあります。まずは製造業に関連して起きた事故や損害賠償の事例を見ていきましょう。
・給食食器視力障害事故
まずは2000年8月10日に奈良地裁で提訴が起きた事例です。当時小学3年生だった女児が、給食で使われていた強化耐熱ガラスの食器が落ちた際に飛散した破片で右目の行為障害を負いました。その結果ケガを負った原告側が加工販売業者や国に対して訴えを起こし、結果的に約1,000万円の賠償請求がおりました。
・エアバッグ暴発負傷事故
こちらは平成19年12月5日提訴された事故ですが、あるカーオーナーがエアバッグが暴発したことによりケガをしました。エアバッグに欠陥があったので製造物賠償責任を問う訴えを起こしましたが、結果的に約500万円の損害賠償が認められました。
・焼却炉火災事件
2004年9月9日には焼却炉による火災をめぐる裁判が起こされました。問題となった焼却炉はバックファイヤという危険な現象が発生する構造的欠陥がありましたが、メーカーはこの欠陥について購入者に伝えることはありませんでした。そのため購入者側の従業員がやけどを負ったほか工場が損傷し、結果的に約2,000万円の賠償が認められました。
このように製造業で作られた製品が原因で、その製品の購入者がケガを負ったり死亡することがあります。そのようなケースでは製造者側の責任が問われて多額の賠償金が請求されることがあります。紹介した訴訟事件はすべて後述するPL法に基づいて起きた訴訟です。
ちなみに上記のエアバッグ事件については構造的欠陥が認められ、焼却炉については危険性に関する指示・警告義務をしなかったことへの過失が認められました。また給食食器に関する事件では構造的欠陥はなかったものの、破片の危険性についての情報提供がなかったために表示内容への欠陥が認められました。
このように製造業では製品そのものの安全性を確保することはもちろん、製品の安全性やリスクに関する十分な情報を示さないと過失が問われて損害賠償が起こされる可能性があるので、製造業従事者は製造から販売の過程でかなり注意しなければなりません。
状況によっては製品の欠陥による消費者の被害が起きた結果製造業者側が犯罪者になることもありえます。刑法第211条によると、製品の問題を把握しながら市場に流通させたり適切な対応をしなかった場合は「業務上過失致死傷罪」に問われる恐れがあります。
製造物責任法(PL法)ってどんな法律?
製造業従事者が特に意識すべき法律があります。それは先述の製造物責任法(PL法)という法律ですが、これは製造された製品に欠陥があって、それによってもし誰かの生命や身体や財産にダメージが生じた場合に製造業者の責任が問われるというものです。PL法では欠陥について過失か故意かは問われないので、ある意味損害賠償請求しやすい環境を作る法律と言えます。
もともとこの法律が1995年に制定されるまでは、民法によって製造物の欠陥に関するトラブルが扱われていましたが、過失を立証することが必要であったため、消費者が製造業者の過失をつきとめて損害賠償を請求するのは非常に難しいことでした。
2.社員も損害賠償請求されることがある!?

会社が製造したものが消費者などに被害を与えた結果、会社に損害賠償が求められることは珍しくありませんが、会社の中で社員が所属会社から損害賠償を求められるというケースもあります。ただし損害賠償が認められるケースにはある程度条件があります。この点を理解するにはまず労働基準法第16条について知っておく必要があります。
労働基準法第16条と損害賠償
労働者への損害賠償に関する規定は労働基準法第16条に見られます。この条項には以下のような点が定められています。
「労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません」
つまり「途中で業務から離れたら違約金を払ってもらう」とか「もし会社に損害を与えたら○○万円支払うように」といった内容を契約書に盛り込んではいけないということです。これだけ見ると、労働者の業務上過失による損害の賠償責任は労働者にはないように思えるかもしれません。しかし実際は違って、会社が労働者に損害賠償を求めることは可能です。
16条で規定されているのはあくまで「事前に決定しない」という点であって、もし労働者の意図、あるいはミスで労働契約上の債務不履行が発生した場合、会社がその労働者に損害額を支払ってもらうのは禁止されていません。
とはいえ人間はミスするものなので、軽いミスに関しても常に業務上の過失責任を問われるわけではありません。この点に関しては「損害の公平な分担」という理念があります。これは「業務は会社による決定事項なので、通常予想される経営リスクは会社が負担するのが公平」という考え方で、これをもとにした判例もあります(名古屋地裁 大隈鐵工所事件)。
しかし労働者の重大な過失や故意の行動による損害発生についてはこの考え方は適用されず、損害賠償請求が発生する可能性が十分にあります。
実際の損害賠償事例
労働者に対して損害賠償請求が通った事例を一つご紹介しましょう。昭和62年7月27日判決(名古屋地裁)の事例ですが、工作機械の製造販売を行う会社が深夜労働中に居眠りした従業員が高額な機会を破損したとして、従業員に対して1,110万円の損害賠償請求をしました。
会社が損害軽減措置をとっていなかったことや深夜勤務中であったことなどが考慮されましたが、従業員の居眠りは7分間も続いたことから軽過失ではなく重過失があったとして、最終的に約83万円の損害賠償が認められました。
このように社員が損害賠償を受ける事例は実際にあるので、製造業従事者は損害賠償リスクを回避する対策を取る必要があります。もちろん意図的に会社やクライアントに損害を与えるのは論外ですが、業務上過失という観点からも注意が必要です。
3 .まとめ
日本は製造業が非常に多いため、製造業にまつわる訴訟や判例はたくさんあります。会社側はPL法を強く意識してモノづくりの安全性を追求する必要があります。安全な製品を作るだけでなく消費者の使い方を想定した製品表示も心がけなければいけません。
また会社側だけでなく従業員の過失による損害賠償のケースもあります。製造業に従事する人は会社側であれ従業員側であれ、業務を遂行する上でまず安全を何よりも優先すべきと言えるでしょう。ちょっとした業務上過失が取り返しのつかない事態を引き起こすこともあるので、この点を意識して作業に臨みましょう。