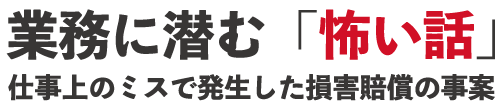会社が提供するサービスや販売する商品には安全性が求められます。もし、役員や従業員による過失が原因で大きな被害が発生してしまったら多額の損害賠償請求や大幅なイメージダウンが起きることがあります。額によっては会社が傾くほどの損害が出ることもあり、最悪の場合は会社が廃業に追い込まれてしまうというケースもあります。
この記事では実際にあった過失に伴う破産・廃業事例を取り上げたいと思います。
1.損害賠償やイメージダウンによる破産の事例

会社の業務に関連して従業員や役員が過失を起こすと最悪の場合、会社が破産してしまう場合があります。そのような事例を2つほどご紹介しましょう。
・フーズ・フォーラス
「焼肉酒家えびす」を経営していたフーズ・フォーラスという会社は、2011年に発生した集団食中毒により死者が発生し、信用を失ったことがきっかけで廃業に陥りました。本社や関係店舗は業務上過失致死容疑で強制捜査され、富山県からは一部店舗の無期限の営業停止処分を受けました。
イメージが大幅にダウンした同社は、店舗の再開は困難と判断して全社員を解雇して廃業となりました。結果的に東京地方裁判所は同社に対して約1憶6,900万円の賠償命令を言い渡しました。
・京都祇園軽ワゴン車暴走事件
平成24年4月に京都の祇園で軽ワゴン車が暴走して19人が死傷する事故がありました。この事件がきっかけで死亡した運転手の勤務先だった藍染め販売会社は事業停止に追い込まれ、京都地裁に自己破産を申請する準備に入りました。
同社の負債総額は約5億7千万円にものぼるとみられますが、事故の影響で来店客数減や受注減で資金繰りが悪化したことが原因とされています。事業を続けることは難しいと判断した結果です。この事件では管理者責任も問われ女性社長が書類送検されています。
この事件は運転手が持病を持っていたことが原因で起きた過失による事故でした。民事裁判では、運転手の家族と勤務先会社に慰謝料や逸失利益の支払いが命じられました。最終的にこの会社は損害賠償で破産したわけではありませんが、過失をきっかけに破産したことに変わりはありません。
社員の業務上過失と損害賠償問題
京都での暴走事件に見られるように、実際にトラブルを引き起こしたのが会社側の責任ではなく、従業員の過失であったとしても、会社がその責任を追及されることがあります。民法715条には「使用者責任」というものが規定されていて、従業員の起こしたトラブルに関与している会社も損害賠償責任を負うことになっています。
例えば、運送会社の社員が不注意で通行人にけがをさせたとしましょう。この場合は運転手の責任が問われて損害賠償責任が発生するのは当然ですが、運転していた車両が会社のものであれば、運送会社にも非があるとみなされやはり損害賠償責任を負います。
このような責任追及の背景には「報償責任の原理」というコンセプトがあります。これは人を雇用する側は従業員による業務内容のリスクも負担すべきであるという考え方です。このように会社が直接トラブルと関係がなくても損害賠償が発生するケースがあるので、会社は従業員の安全への意識を高める努力を欠かしてはいけません。
2.まとめ
損害賠償トラブルが原因で破産に追い込まれた会社の事例を紹介しました。紹介した事件は2つとも死者が出る大きな事件でしたが、そこまではいかなくても損害賠償が原因で会社が倒産に追い込まれるケースはいくらでもあるでしょう。
例えば、情報漏洩問題などで莫大な損害賠償請求がなされれば一気に経営悪化に追い込まれる恐れがあります。そのため会社は従業員の業務内容や遂行の仕方、扱っているデータなど関連する物事に関して安全意識を高める必要があります。適切な予防策を講じることで不必要なリスクを招かずにすむでしょう。